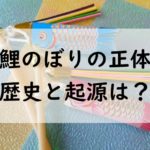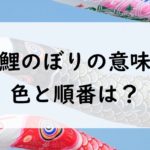東京住まいの方は、こどもの日は『柏餅』ですよね。しかし、関西方面は、粽(ちまき)を食べます。では、こどもの日に『ちまき』を、なぜ、関西人は食べるのでしょうか
今回は、怖い!ちまきの由来と、端午の節句に『ちまきを食べる本当の意味』を徹底解説をします
編集部の独断と偏見が混ざった内容になりますが、別に『ちまきが縁起が悪い食べ物ではない』けど『食べ方に注意が必要』という結論です
ちまきを食べる時に、してはいけないことがあり、こどもの日にやってはいけないと考えられる事ががあります
では、まずは、最初に、一般解釈の『粽(ちまき)の由来と意味』から説明します
なぜ?ちまきを食べるの?こどもの日の食べ物の粽とは?
こどもの日に、ちまきを食べる風習は主に関西圏の地域になります。関西は昔、京都に都があり、古代中国の端午の節句の行事が、奈良時代から続いています
格式と文化を大切にする京都は、ご丁寧に古代中国の端午の節句のルールを守り、1000年以上、端午の節句の食べ物として、ちまきを食べています
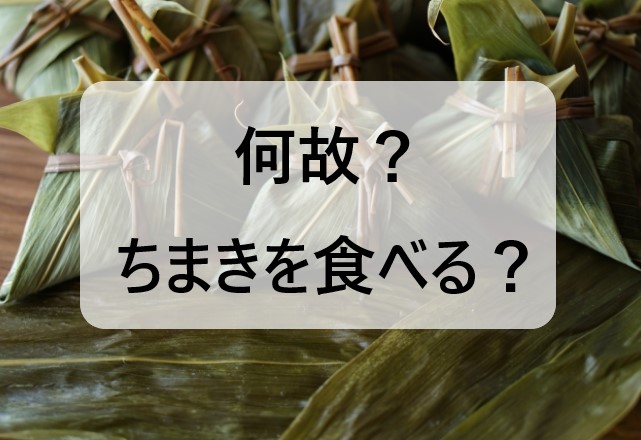
| ちまきの歴史 | 歴史 |
| 奈良時代(710年頃~) | 端午の節句が日本に伝わる |
| 和妙類聚抄(931年頃~) | ちまきが辞書に登場 |
| こどもの日(1949年制定) | 5月5日が子供の日になる |
正確なお話をすると、端午の節句とは旧暦の5月5日頃、現在の6月5日頃に行われた『厄払いの儀式』になります
6月は春と夏の季節の変わり目であり、風邪や伝染病が多く、昔の人は『魔の物による仕業』と考え、端午の節句に厄払いを行っていたのが、事の始まりです
奈良時代に『粽』が存在したか不明ですが、現存する書物では、931年頃の書物に『和妙類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』という現在の辞書、ネットならWikipediaのようなものが発見されています
和妙類聚抄(わみょうるいじゅしょう)によると、葉っぱでもち米を包んで煮た食べ物が『粽(ちまき)』を記載があり、現在とレシピが、差ほど変わらない内容で紹介されています
それから、1000年ほど、時間が経過してから1949年に、端午の節句(男の子のお祝い)と桃の節句(女の子のお祝い)を合わせて、こどもの日となりました
以上の経緯と流れで『端午の節句に食べていたお祝いの食べ物』として、ちまきが食べられています
ここまでの話が、一般的な解釈の『粽(ちまき)、こどもの日の関連性』になります
なるほどね!古代中国の魔除けの儀式から始まって、現在まで続いているのね!ということで、だいたいの話は正しい事だと言えます
でも、なんで?なぜ、ちまきを端午の節句に食べていたの?と、不思議に思いますよね。次からが、ちまきの怖い話の内容になります
ちまきを食べる由来は何?ちまきに意味があるの?

ちまきを食べる由来は、古代中国の楚の時代の賢い政治家であり詩人であった屈原のように、立派に出生して欲しいという願いから、ちまきを食べるようになったと由来が説明されます
ちまきは、賢い人物の屈原(くつげん)が大好きだったとされる食べ物です。ちまきを食べると『屈原のように立派になれる』という解釈になります
簡潔に言うと、偉い人に将来なる事を願って、子供のお祝いとして食べるという感覚が現在の『ちまきの意味』と言っても過言ではありません
しかし、我々、編集部は偉い人物とされる屈原(くつげん)の一生をお調べした結果、本当に『屈原のように子供が将来なっても良いのか、正直、微妙という結論に至りました
ちまきを食べる理由は『屈原(くつげん)』の命日に供養する事が目的!

端午の節句の時期に、なぜ、ちまきを食べるのか。国への忠誠心が高く、非常に賢かった屈原(くつげん)の死を供養する目的として『ちまき』を川に流したことが、ちまきと端午の節句の由来の関係性になります
中国では、ちまきが『忠誠心の象徴』として意味づけされ、日本国内では『子供の立身出世を願う』と少し異なった意味合いで認知されています
下記に、ちまきが好物であった屈原(くつげん)の生涯を一覧にしました。
編集部が『ちまきの怖い話』としてとらえた理由、そして、ちまきの事を私たちが『大きな勘違い』をしている点に気が付くと思います
| 屈原 | 読み方:くつげん |
| 出身階級 | 公族(名門一家出身) |
| 【1】戦争の戦略を提案 | 王に受け入れられず戦争に大敗 |
| 【2】左遷させられる | 王は大敗後も秦の国を信じる |
| 【3】楚の王が拉致される | 楚の王が秦に裏切られる |
| 【4】楚が秦の属国になる | – |
| 【5】国を追われる | 秦の人に国を追われる |
| 【6】自殺する | 川に身を投げる |
屈原のように立派に出世して欲しいと願いがこもっているのが、ちまきとされますが
まず、第一に屈原は名門一家の公族出身です。最初から、親ガチャに成功している人であり、将来、国を背負う人物として育てられている点が、庶民からすると納得きませんよね
ただし、屈原は頭が良かった事は間違いなく、紀元前312年の丹陽・藍田の戦い時に『秦の国に、ハメられる可能性がある』と、何度も、王に進言をしたけど、受け入れてもらえず、結局、この戦いで楚が大敗をします
屈原の生涯とは『敵国の秦の国を信用しちゃダメだ』と王様に言ったけど、王様がそれを聞かず、自分の国が乗っ取られてしまいます
乗っ取られた後は『秦の国を危険と判断する人物』として、国を追い出され、追われる身となります
そして、最終的に、川に身を投げ込み『自殺して生涯に幕を閉じた人物』です
広い国土を持つ中国なら、逃げ伸びることができれば、屈原は身を隠してひっそりとその後を過ごしたでしょう
しかし『反逆者として復讐をするかもしれない人物』を新体制の国王が許すとも思えません
川に飛び込んで自殺というのは、秦の国の歴史資料にある事柄であり『普通に殺されて、死体を川に投げ込まれた』というのが実態はないでしょうか。
屈原の水死体を当時の技術で発見し、自殺と判定する方法が本当にあったととても思えません
むしろ、国からの追ってから逃げる途中で捕まり、処刑されてしまった。首だけ証拠として国へ持ち帰り、そして、体の残りは川に捨てられた可能性の方が高く思えます
当時の古代中国は、火葬がNG。普通は土葬です。水葬は決まった葬式と儀式がなく、通常と異なる死に方を思い『供養が必要』だと考え、川へちまきを流したと考える方が自然です

| 現代版:屈原ルート | 屈原の事例 |
| 【1】親の会社に就職 | 【1】公族に生まれる |
| 【2】会社が乗っ取られる | 【2】国が乗っ取られる |
| 【3】古株と自分が追い出される | 【3】国に追われる |
| 【末路】鬱になって自殺する | 【末路】自殺(他殺説が濃厚) |
話が難しい方向けに、現在社会で例えた例が上記です
最悪のルートじゃないっすか!コレはバットエンドだぞ!と思いたくなりますよね
今風に言うと、親が経営する会社に就職したら、買収を仕掛けてきた企業が現れました
めちゃめちゃ賢かったから、なんとなく相手の狙いが分かり、
会社を守るために社長(父親)に『株を売ったらダメだよ!のっとられるよ!』と言ったんだけど、社長が聞かず株を売ったら、会社が乗っ取られました
その後、古い社員や新体制に反対する幹部が追いだされたという感じじゃないでしょうか
以上の事が、こどもの日と『ちまきの怖い話』になります
おいおいおい!こんな怖い話と縁起が悪い言い方をされたら、こどもの日に『ちまき』が食べずらいじゃないか!と文句が言いたくなりますよね
ご安心してください。みなさん、とても重要な事を見逃しています。こどもの日の『ちまきの食べ方』を工夫しましょう
ちまきの正しい食べ方!ちまきに願いを込めない!

子供の成長、立身出世を願って『ちまき』を食べる事は間違いです。端午の節句の『ちまき』とは、不遇の死をとげた屈原を弔い、供養として食べる事が正しい『ちまきの食べ方』になります
子供が『将来、出世して欲しい』や『賢い歴史上の偉人のようになってほしい』と願いながら食べるのは、屈原の死の話を知ると『ちまきの間違った食べ方』に思えてくるでしょう
屈原は出世はしたけど、殺されたか。もしくは、追われて自殺をしています。将来、子供が『大企業に入って出世』したけど、派閥闘争に巻き込まれて『うつ病、そして、自殺』なんてしてほしくないでしょう
| 【正】 | 供養する思いで食べる |
| 【誤】 | 立身出世を願う |
こどもの日はお祝いで楽しい日のはずなのに、供養する思いを持って『ちまきを食えだと?』と言いたくなりますよね
考え方を、ちょっとオカルトにシフトしましょう

亡くなった屈原は、賢い人物でした。それならば、もし、死後の世界に天国があるなら?それなりに『のし上がったポジション』や『上位の神様になっている』のではないでしょうか
バカじゃない人だったのなら、生前の失敗を糧とし、きっと、天界でビックな立ち位置にいるはずです
屈原の供養を目的に『ちまきを食べてる子供』を天国から見たら『こいつ!俺の事、わかってんじゃん!いい心がけだ』と思い、多少、人生を優遇するように仕向けていただけるかもしれませんよ

だけど、もしかしたら
屈原は俺の好きだった『ちまきはコッチだよ!』『それじゃないよ!』と、おやつじゃない方の粽が好きだったかもしれません
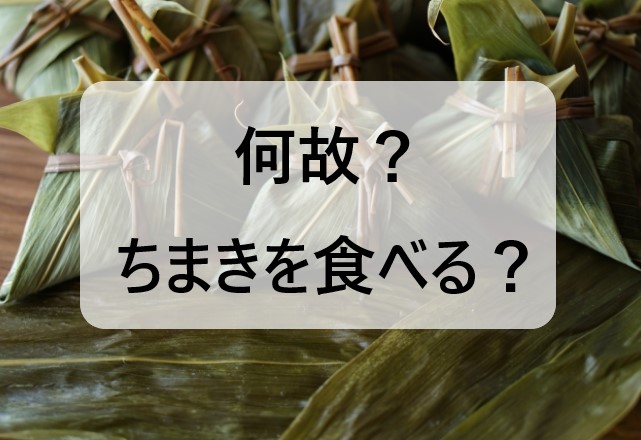
さて、今回は、5月5日。こどもの日、端午の節句に『ちまき』を食べる理由を歴史的な経緯をもとに解説をしました
古代中国の楚の国の屈原(くつげん)の嘆きの死を考えると、ちまきの正しい食べ方は『供養』であり『屈原のように立派に出世』と願わずに食べるか、普通に『何食わぬ顔で食べる事』が正解になります
こどもの日に、ちまきを食べてもいいけど!何も願わず、普通に、甘くてちょっと冷たくて旨いじゃん!と思いながら食べましょう