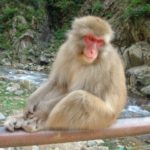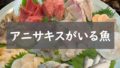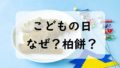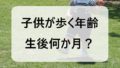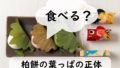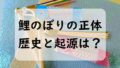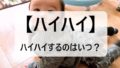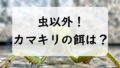触るとクルクルと丸くなる不思議な生き物がダンゴムシですよね
ダンゴムシはどうして丸くなるの?この疑問を解決するヒント⇒子供に聞かれて説明したい時の参考になる情報をたっぷり紹介。ダンゴムシの体のつくりや構造も含めて一気に解説します
ダンゴムシの体のつくりとは?どんな構造?
ダンゴムシとは、丸くなった姿が団子に似ている事からネーミングが決まった生き物です。そもそもダンゴムシは、体に節(ふし)があり節と節の間に薄く、柔らかい皮があります。ダンゴムシは体の構造上、丸くなる事ができます
日本にいるダンゴムシは種類が少なく、ほとんどがオカダンゴムシという種類です

| ダンゴムシ | 特徴 |
| 頭部 | 1節 |
| 胸部 | 7節 |
| 腹部 | 5節 |
| 尾部 | 1節 |
| 触覚 | 2本 |
| 足 | 14本(7対) |
ダンゴムシの体のつくりを軽く一覧にまめました。なぜダンゴムシは丸くなる事ができるのか。胸部に7節、腹部に5節とこの部分に節+間の皮がたくさんあるよ
こうやって考えると、一番、丸くなれる箇所はこの部分になりますよね。この体のつくりは、海にいる「海老」とそっくりです
子供になんで丸くなれるのか。ココを聞かれたときは「海老と一緒だよ^^」とこの回答がすぐに理解できる方法の1つかと思います
【従来】ダンゴムシが丸くなる理由とは?
ダンゴムシが丸くなる理由は主に2つ考え方があり、1つ目が「外敵から身を守る為」というものです。実際、蟻(アリ)に襲われたダンゴムシは丸まっている=防御しています
| 天敵 | 強さのレベル |
| 鳥 | 天敵 |
| カナヘビ | 強敵 |
| トカゲ | 強敵 |
| ヒキガエル | 強敵 |
| 蟻 | 丸くなって防御 |
こちらが、ダンゴムシを食べる!外の外敵たちの一覧です。鳥やトカゲ、カエルにダンボ虫は狙われ食べられてしまいます
ダンゴムシは自分より大きな体の生き物に食べられちゃうなら「丸くなる意味なくね?」と思いませんか
ダンゴムシが丸くなる理由は、図鑑やネットに「敵から身を守るため」と説明がありますが、それだけの理由で、進化し生き残ってきたわけではないです
【現在】ダンゴムシが丸くなる理由とは?
ダンゴムシの研究は多くは行われていません。従来までは「丸くなる=身を守る」という考え方が主流でしたが、今では別の理由でダンゴムシが丸くなると考えられています
| ダンゴムシ | 強さのレベル |
| 湿度40% | 丸くなる ⇒続くと死滅する |
| それ以上の湿度 | 活発的に活動 |
以前、中学生がダンゴムシを飼育し、文部科学大臣賞をとった内容です
その研究記録によると「ダンゴムシは湿度が下がると死滅する=40%台が最も多い」という内容ですが、その時の行動・様子に「ダンゴムシが丸くなる」といった特徴が多々、あげられています
実際にダンゴムシは「丸くなる事」で、寒さ、暑さをしのいでいるという考察と研究も多く、ただ、身を守るだけで丸くなっているわけではない事がうかがえます
このお話は「進化」という視点からすると『敵に襲われる回数が多かった⇒気温・湿度の変化に対応する為』に、体が丸くなる構造になったと考えた方が正解なような気がします
ダンゴムシが丸くならない!なぜ?ダンゴムシとワラジムシの違いは?
なるほど!こういった理由からダンゴムシは丸くなるのかと、ある程度、伝わったかと思います。しかし、触ったり捕まえた時に「丸くならない奴」がいますよね
丸くならないダンゴムシの正体は「ワラジムシ」というよく似た虫です。

| 内容 | ダンゴムシ | ワラジムシ |
| 特徴 | 丸くなる | 逃げる |
| 体長 | 15mm | 12mm |
| 分類 | ワラジムシ亜目 オカダンゴムシ科 | ワラジムシ亜目 ワラジムシ科 |
| 生息地 | 全国 関東以南、四国・九州 | 全国 北海道・東北 |
ダンゴムシとワラジムシは、大きさも近く、同じワラジムシ亜目です。ワラジムシはワラジの形をしているといっても、見てすぐにダンゴムシとの見分けは難しい(写真はワラジムシです)です
一番わかりやすい違いは、触ったら丸くなるのがダンゴムシ。逃げるのがワラジムシです。この違いは進化の過程で取ってきた行動に違いとされ、ダンゴムシより当然、ワラジムシの方が足が速いです^^
そのほか、参考になる情報はダンゴムシとワラジムシの生息地域の違いです
どちらも日本全国で目撃情報がありますが、ダンゴムシは関東より南、ワラジムシは東北・北海道の寒い地域の方が多く存在しています