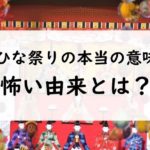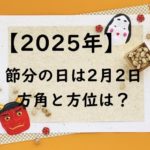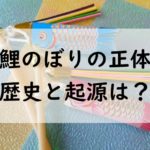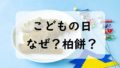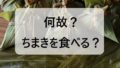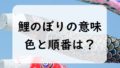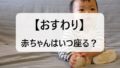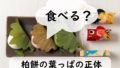ココが違うよ!疑問に思った「しらすとちりめんじゃの違い」はコレで完璧!しらすとちりめんの事をしたい方向けに、シラスとジャコの差を徹底調査+詳しく解説します。
しらすとじゃこの共通点は?魚は同じイワシ→季節によってイワシの種類は違う!
しらすと、ちりめんじゃこはどっちも同じ「イワシの稚魚(子供)」の総称で、使うイワシの種類は季節によってバラバラです。たとえば、春ならカタクチイワシ、秋・冬から漁獲されるマイワシ、ウルメイワシの稚魚を使っています
つまり、「しらす」も「じゃこ」もイワシの子供である事は共通事項です。

イメージわかない方はコレを。生姜と醤油で食べると「ツルっとして旨い」、それが生シラス。静岡の駿河湾付近の生シラス丼は絶品ですよね!この小魚の正体が、カタクチイワシやウルメイワシの稚魚です
しらすとちりめんじゃこの明確な違いは地域での呼び名の差!
「しらす」と「ちりめんじゃこ」の違いは、関東・関西で言い方が異なる!関東方面=しらす、関西方面=ちりめんじゃこ!と呼ぶのが一番わかりやすい違いです
| しらす | ちりめんじゃこ | |
| 地域 | 関東 | 関西 |
| 漢字 | 白子 | 縮緬雑魚 |
| 意味 | 白子=白い稚魚 | 縮緬=細いシボがある織物 雑魚=小さい魚、煮干し |
関東方面は「しらす」と呼び、シラスを漢字にすると「白子」です。白子とは、フグ、タラ、アンコウの精巣を意味する事もありますが、イワシを含む小魚の稚魚、ニシンやアユ、イカナゴなど。これら小さい魚の子供のことをまとめた白子という意味があります
「ちりめん」と「じゃこ」の違いは「縮緬=じゃこの集合体」、「じゃこ=干した小魚」
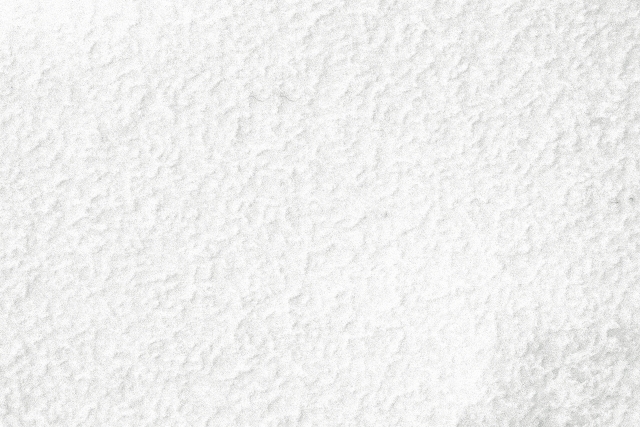
要するに関東方面では「小魚の稚魚=しらす」と言う文化があったと考えるとわかりやすいです。反対に、大阪方面では「ちりめん」という言葉を使いますが、チリメンを漢字にすると「縮緬」、縮緬とは織物の技術や模様の一種で「すっごい細かく縫う技術、主に絹を使った織物」の事です
簡単に言うと上の写真のようなテクスチャーが縮緬(ちりめん)であり、この模様に「大量に干した小魚(しらす)が似ている=ちりめん」と呼ぶようになったのが起源と由来です
この縮緬という織物の技術は西暦1600年前後に、南蛮貿易で日本に伝わったとされ、1700年頃の大阪は「天下の台所」と呼ばれた日本の貿易地点。ずっと昔から縮緬という言葉は、そもそも存在していた!というのが1つのポイントです
ちなみに、じゃこを漢字で書くと「雑魚(←ザコとも呼びますが、ジャコ)」であり、雑魚には「煮干し=小魚を干して煮たモノ」と意味があります
実際にある商品の「ちりめん山椒」は山椒で煮た茶色い煮物、佃煮の1種です。この商品で有名なのは京都の「京佃煮ちりめん山椒」や「はれまのちりめん山椒」と、こちらも関西方面が発祥です
正確に定義するとしたら「じゃこ=干した小魚(少量)」の事であり、このジャコの集合体!「大量にあるジャコ=ちりめんじゃこ」と細かく分類して考えるとわかりやすいです
このように考えると「なるほど!関東と関西で言い方が違っても、全然おかしくない」と思えますし、歴史的な経緯が思ったより、大阪方面の方が歴史が深い感じがあります
ここまでに「しらす、ちりめんじゃこの違い」を説明しました。次は「それなら、釜揚げしらす、しらす干し、ちりめんじゃこ」は何が違うの?って話をしますね
生シラス!釜揚げしらす、しらす干し、ちりめんじゃこの違いは水分の量!乾燥具合の違い!
シラス(じゃこ)は「漁獲する→茹でる→天日干しをする」という方法で食品になります。釜揚げしらす、しらす干し、ちりめんじゃこ。この3つの違いを簡単に言うと、乾燥させた時の水分量の違いであり、下記の表に乾燥具合をまとめました。一般的なシラス、ジャコ製品はこんな感じの乾燥がされてるのね!と思ってくださいね
| 状態 | 水分の割合 | 卵で例えると? | |
| 生しらす | 取れたて新鮮 | – | 生たまご |
| 釜揚げしらす | 軽く茹でる | 75~90% | 半熟たまご |
| しらす干し | 弱干し | 65~75% | ゆでたまご |
| ちりめんじゃこ | 中上干 | 50~65% | 固ゆで卵 |
| ちりめんじゃこ | 上干 | 35~40% | 激!固ゆで卵 |
この表がシラス製品のよくある「呼び名の分類」です。茹でた後、太陽の光で干したときに「残ってる水の量」の違いによって、言い方を変えているというのがシラス業界の事情です
水分の割合をパーセンテージで言われてもイメージつかないよ!という方は、一番、右に「卵」を例にしてあてはめました。実際のゆで卵の水分の割合とは違いますが、ざっくりこれくらいの食感・固さの違いね!とイメージしてもらえればと思います
生しらすとは「水揚げ当日」のとれたて新鮮なイワシの稚魚

生シラスとは、新鮮なとれたてのイワシの稚魚の事です。シラスは、傷むのが早く消費期限が短い魚、通常、生シラスは「漁獲した当日」でなければ食べられません
茹でる前の色は「透明」であり、今日取れたシラスなら生シラス丼にして食べれます。このメニューは、静岡県の駿河湾や神奈川県の江の島で名物です。食べたい方は足を運んでみるのもありです
釜揚げしらすは水分は多め!煮沸(茹でる)→冷やしたシラス

漁獲したシラスはそのままでは日持ちしません。そのため、シラスを茹でるといった方法で、長く保存+新鮮さをなるべく維持した形が、釜揚げしらすです。製造メーカーによって多少の違いはありますが「水分率:75~90%」が目安です
釜揚げしらすを、料理で使うなら「しらす丼」や「小松菜のお浸しの材料」として使うとちょうどいい具合です
しらす干しとは『釜揚げしらすを乾燥』させたモノ!水分率は65~75%前後

釜揚げしらす、茹でたシラスを「天日干し」や「乾燥機」で干した製品が「しらす干し」です。釜揚げしらすは茹でた後、冷やして保管ですが、しらす干は+乾燥させるという工程が加わり「水分率:65~75%」の商品が多いです
ここまでに、釜揚げしらす、しらす干しと名前が出てきましたが、関東方面の呼び方がコレです。大阪など関西方面、それより西の地域では「これらの商品=ちりめん」と、まとめて呼ぶのが一般的です
ちりめんじゃことは「より乾燥させた商品」が多い!水分率は35~40%

ちりめんじゃことは、しらす干しよりももっと乾燥させる「中上干」や「上干」といった水分率が35~40%前後の製品の事です
関西方面では、ごはんにのっけて食べるといっても「ちりめん山椒」や「京都風!じゃこの佃煮」という風に、そもそも料理の作り方と、食べ方が乾燥させていた方がメリットがあるメニューが多い。ココも特徴の1つです
さて、色々とシラスとチリメンの違いについて説明しました。地域によって呼び名は違う!という事情がありますが、年々、ネットの普及でココで紹介した名前の呼び名が一部、曖昧になっている事情もあります
今後はもしかしたら「白い小魚=シラス」、「乾燥させり、煮物にした小魚=ちりめん」のように白と茶色の違いで言い方が統一されるかもしれませんね。白いのがシラスで、茶色いのがチリメンであっても内容的には確かに正しいので、会話の中で使う言葉としては、間違ってない気がします